| 大村の歳時記シリーズ | 竹炭つくり |
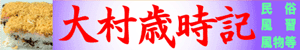
 |
||||||||||||
| 下部はステンレス製の無煙炭化器、燃えているのは太い孟宗竹(もうそうちく) | ||||||||||||
|
竹炭つくり(ちくたんつくり)
時季について |
||||||||||||
| 初回掲載日:2024年12月22日、第二次掲載日:12月29日、第三次掲載日:2025年1月3日、第四次掲載日:1月8日、第五次掲載日: 月 日、第六次掲載日:4月1日、、第七次掲載日: 月 日、、第八次掲載日: 月 日、 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 大村の歳時記シリーズ | 竹炭つくり |
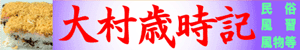
 |
||||||||||||
| 下部はステンレス製の無煙炭化器、燃えているのは太い孟宗竹(もうそうちく) | ||||||||||||
|
竹炭つくり(ちくたんつくり)
時季について |
||||||||||||
| 初回掲載日:2024年12月22日、第二次掲載日:12月29日、第三次掲載日:2025年1月3日、第四次掲載日:1月8日、第五次掲載日: 月 日、第六次掲載日:4月1日、、第七次掲載日: 月 日、、第八次掲載日: 月 日、 | ||||||||||||
|
||||||||||||