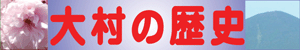1)石仏と線刻石仏とは何か
石仏とは
石仏とは字の通り、石で造られた仏像です。ただし、石仏には色々と種類があります。まず、本当におおざっぱに大別すると、次の二通りと思われます。
(A)自然石をそのまま使って仏像を製作する。
(B)切石から、さらに加工して仏像を製作する。
上記の(A)をさらに、分けると、主に次の通りと思われます。
1,磨崖仏(まがいぶつ)=自然の岩壁を直接削って仏様を造ったもの。
(大分県臼杵市にある『国宝臼杵石仏』が有名。武留路町・仏岩三社大明神の線刻石仏三体も磨崖仏)
2,単体の自然石の形に合わせてレリーフして仏様を彫刻したもの。
3,単体の自然石の表面に線刻して仏様を描いたもの。(福重の線刻石仏は全部この方式)
線刻石仏とは
線刻石仏とは、石の表面に線模様で彫った仏像のことです。ただし、私自身、実はこの件ついては全般にわたって現在調査中です。しかも、下記の(1)については、私が勝手に付けた仮称です。線刻石仏全体まだまだ調査中の事柄で今回このページでは、線刻の線の特徴を述べる程度にしておきます。
(1)(仮称)線刻彫り技法
この線刻の技法は、結論から先に言えば、まだ調べきれていません。私が見た範囲で自然石に描かれた線は、下記(2)タガネ彫り技法に比べ幅が均一です。太い線は太いなりに、細い線は細い線なりに、ほぼ同じ太さで描かれています。どうやって、このような均一の線が自然石に彫れるのか、地元でも様々な意見が出ています。
この線刻彫り技法について色々な意見の中から、「タガネ彫り技法より古くて、高度な技術を持った人(石工、仏教僧侶)が、彫ったのではないか」との感想も出されています。先に申し上げた通り、この線刻彫り技法の詳細は不明です。ただ、下記(2)タガネ彫り技法と違う技法で彫られた感じはしています。この件、分かりしだい、この項目を改訂する予定です。
ご参考までに、素晴らしい線刻彫り技法は、(右上写真の弥勒寺の不動明王を始め上八龍の線刻石仏、下八龍の線刻石仏ページなどをご覧下さらないでしょうか。(念のため右上写真の弥勒寺の不動明王は分類上、福重の線刻石仏14体の中に入れていませんが、自然石に線刻されたと言う点では同じ技法です)
なお、これらの線刻石仏は、狭い地域にまとまってあること自体けっこう珍しいことですが、まだまだ長崎県内でも大村市内でも、知られていない存在の石仏でもあります。
(2)タガネ彫り技法
極簡単に書きますと石工さん(木工用なら大工さんも)が使用されているようなタガネで彫ったものです。ただし、タガネの種類は沢山あります。また、石工さんオリジナルのタガネも当然ありますから、どのタガネで線刻石仏は彫ったものと特定するのは困難です。
私が見てタガネで彫ったものと思われる線刻石仏は、線の幅にややムラがありました。もちろん、彫った人の技術の上手下手も当然影響あるかと考えられます。ただし、例えば左手でタガネを握り、右手で金槌を打ちおろしながら線を彫ったと思われますが、この方法なら少し線の幅にムラが出やすいのかなあと想像はできます。また、線刻石仏の製作上、上記(1)(仮称)線刻彫り技法より、新しい技法ではないかとの感想や意見もあります。
以上が、石仏の大別と線刻方法の技法についてのあらましです。今回のテーマの福重の線刻石仏14体は、全部自然石に線刻された石仏です。これらの線刻石仏の線の彫り方は上記(1)、(2)とも二通り、どちらもあります。
2)CG写真で見る福重の線刻石仏の特徴
この項目、まず下記6枚のCG写真からご覧頂けないでしょうか。念のため、実物を肉眼で見ても自然石に彫られた線は見えてはいます。しかし、写真にした場合、ただの石のようで線が見えてきません。そのため、下記CG写真は、線刻部分だけを写真加工ソフトで、なぞるようにして白色や黄色で色づけしたものです。(詳細な(作成方法などの「)CGの石仏写真について」は、ここから参照を。また、実物のCG写真は、いずれもA3サイズ以上でも精密に見える画像だが、下記はホームページ用に極端に縮小している)
なお、写真縮尺サイズが各々違うため、見た目の大きさは参考になりません。大きさや石仏の詳細を知りたい方は、写真下側にあるリンク先から、ご参照願います。そのリンク先ページに各々の石仏の詳細説明とCG写真のやや拡大版があります。また、下記の6体の石仏は、全て大村市福重地区(旧・福重村、現在の福重小学校の校区内10町)に現存する線刻石仏です。(3)のみが(旧・矢上郷の)福重町(私有地)に存在し、それ以外の(1)、(2)、(4)、(5)、(6)は弥勒寺町(私有地)にあります。
福重地区には、2009年3月16日に新発見された「清水の線刻石仏」(弥勒寺町)を含めれば線刻石仏の種類としては、合計14体あります。上記(1)〜(6)の6体は、その代表例として掲載しています。他の弥勒寺町の「石堂屋敷の線刻石仏A、C、E、F、H、I」、「清水の線刻石仏」も、各々細部の違いは当然ありますが、上記(4)〜(6)の「石堂屋敷の線刻石仏B・D・G」と、ほぼ全体の形は似ています。なお、「石堂屋敷の線刻石仏C」のみ、現在行方不明で欠番扱いにしています。
胸から腹部にかけての線刻模様にご注目を
<共通している線刻模様>
上記の写真、代表例6体でも、お分かりの通り、線刻石仏の様式・形式に若干の違いはない訳ではありませんが、下記の主な特徴点が、ほぼ共通してあります。まずは、上記写真をサッと見た印象だけをこの項目では書き、後の項目で「なぜ、こんな姿・模様なのか?」、「どのような仏像、神像、神仏習合像なのか?」みたいなことを詳細に掲載したいと考えています。
1,手印がなく納衣の下で拱手している姿という珍しい線刻石仏
上記写真6枚の胸から腹部にかけての線刻模様を、ご覧頂きますと直ぐにお分かり頂けると思いますが、全て同じ特徴があります。それは、手印(「用語解説参照」)がなくて、お椀を伏せたような形で拱手(「用語解説参照」)している両手を納衣(「用語解説参照」)で被う=納衣の下で拱手している姿という珍しい様式・形式をした石仏です。特に、この「高さのある大きなお椀を伏せたような線刻模様」に、ご注目願います。
これが、福重の線刻石仏の最大の特徴点とも言えます。また、この点などが今までの専門家や郷土史愛好家含めて不明な点で、「福重の石仏、最大の謎」とも言っている理由の一つでもあります。(注:以降難しい言葉などは、各々リンクは張っていない場合もあるが、「用語解説」から参照願う)
2,同じような納衣(袈裟)と通肩
上記6枚写真の通り(1)上八龍の線刻石仏と(3)石走の線刻石仏には、光背があるのが特徴です。しかし、この光背部分の模様を除けば全部の線刻石仏の姿そのものは似ています。当然、14体全部の線刻石仏に同じような納衣(袈裟)と通肩があります。ただし、納衣(袈裟)や通肩の大きさ、長さには違いがあります。
胸元の二本線で表している通肩の長さや形も仏像研究の一つの対象のようですが、今回この項目の場合は長さより形状が似ている点のみを見て頂けないでしょうか。(通肩は上記の「用語解説」の通りですが、石仏調査などの時は単に胸元にある納衣の両側二本線を指している場合もある)この通肩の模様違いによって石仏の制作年代、その制作者も違うと推定されているのに福重の線刻石仏の場合、同じような納衣と通肩の姿(模様)が全体として似ている特徴点もあります。
3,蓮華座がない
仏像は全部がぜんぶでは当然ありませんが、けっこう多くが蓮華座(れんげざ)の上に乗っておられます。しかし、福重の線刻石仏14体は全て蓮華座が線刻されていません。ただし、蓮華座がないから直ぐに短絡的に「仏像ではなく神像では」と言うものではありません。しかし、「神像あるいは神仏習合像の可能性もあるかもしれない」と言う一つの根拠にはなっています。
あと、私の推定ですが、木製の仏像に比べたら自然石に線刻するのは、なかなか技術的に困難さもあり、蓮華座を線刻しなかった可能性もあったのではとも思いました。ただし、仏像には蓮華座含めて色々な意味があるので、省略系の模様とも考えられません。全国やアジアの石仏例では、明らかに仏像なのに、同様に蓮華座のない仏像例は沢山あります。
なお、ご参考までに、今回紹介しています線刻石仏と種類が全然違いますし、制作時代も鎌倉時代中期と推定されている弥勒寺の不動明王には、岩座が線刻されています。(弥勒寺の不動明王のCG写真と詳細説明ページは、ここからご覧下さい)
<共通していない線刻模様>
この項目では、福重の線刻石仏(合計14体)で共通していないが、気になるような点を概要だけを列記していきます。「何故こうなっているのか?」みたいな詳細は、前と同じように後の項目で書いていきます。
1,光背がある石仏と、ない石仏
福重の線刻石仏(合計14体)で光背があるのは、2体(「上八龍の線刻石」、「石走の線刻石仏」)だけです。あとの12体に光背はありません。光背とは(「用語語解説」の通り)「仏身から発する光明をかたどった、仏像の背後にある飾り。頭部のものを頭光(ずこう)、身体部のものを身光(しんこう)といい、中国・日本ではこの二重円光式を主体とする」ことですから、仏像の場合、この光背がけっこう多く見られます。ただし、光背のない仏像もありますので一概に、この光背が「ある」、「ない」だけで全ての判断材料にはならないと思います。
2,白毫がある石仏と、ない石仏
白毫(びゃくごう)が、福重の線刻石仏で明確に見られるのが、「上八龍の線刻石」、「下八龍の線刻石仏」、「石走の線刻石仏」、「線刻石仏D」などです。この白毫相とは、(「用語語解説」の通り)「眉間(みけん)にあって光明を放つという長く白い巻き毛」ですから、仏像の場合、この白毫が多く見られます。しかし、福重の線刻石仏には、ハッキリと確認できない、あるいは判断つかないものもあるのです。
3,肩の二重線がある石仏と、ない石仏
線刻石仏の肩付近に二重線があることが分かったのは、「線刻石仏I」の拓本作業をしていた時でした。それ以外にも、調べて見たら、「石走の線刻石仏」がありました。当初、この線について何人かの方に尋ねたところ「その二重線は失敗して彫り直した線ではないか?」との答えもありましたが、その意味ばかりではないようです。先の2体以外に「この石仏にも二重線があるのでは」と思うものも数体あるのですが、やや判断つきかねるので今回これらは挙げないことにしています。
以上、この項目では「2)CG写真で見る福重の線刻石仏の特徴」として、写真6枚を例にあげながら福重に存在する線刻石仏の特徴点を述べました。次の項目では、さらに、なぜ「福重の線刻石仏 最大の謎とは」なとと、呼んでいるのかについて記述したいと考えています。
3)福重の線刻石仏 最大の謎とは
今回の項目は、私の勝手な表現ながら、なぜ「福重の線刻石仏 最大の謎」なとと、呼んでいるのかについて書いていきたいと思っています。念のため、現在考えられている福重の線刻石仏の種類については、後の項目で推論含めて書く予定です。これまで地元の者でも、見学にいらっしゃった方々からも、この特徴ある石仏に対して実に様々な意見、推論や感想などが私の方にも寄せられました。 例えば、
 |
下八龍の線刻石仏(弥勒寺町、白線はCG加工)
<この”拱手した姿”は何と言う石仏か? 最大の謎>
|
・「両手を納衣で隠して拱手しているので神像ではないか?」
・「全体の形自体は、どこでも見るような如来系の石仏ではないだろうか?」
・「あなた方は石仏(仏像)と呼んでいるが、仏像と言うより神像あるいは神仏習合像ではないか?」
・「こんなに沢山あるのに蓮華座が一体もない石仏は、見たことないなあ」
・「これは本地仏を表示するための仏形(けぶつ、「用語解説参照」に似たような、同じような仏像があった」
・「この形は修業中の僧侶を表しているのでは?」
などです。また、極一般論として「神像ならば、こんな狭い地域に沢山ある訳がない。仏様なら一か所に沢山ある所も今まで見てきたが・・」などの感想もありました。
さらに熱心な方は、写真数枚を持参されて「福重の石仏は、この仏像、神像に似ている。参考にならないか」などと具体的に教えて下さった例もありました。しかし、どなたも今まで確信持って断定的に(正確に)、「この福重の石仏は・・・と言う種類の仏像(あるいは神像)だ」みたいなことは聞きませんでした。つまり、今なお誰も明確に分かっていない「謎の石仏」と言うことです。
これまでと重複した書き方になりますが、改めて福重の線刻石仏の特徴を挙げます。それは「2)CG写真で見る福重の線刻石仏の特徴」か、代表例として右上側写真(下八龍の線刻石仏のCG写真)を再度ご覧下さるとお分かりになるかと思いますが、胸から腹部にかけて手印がなくて、お椀を伏せたような形で両手を納衣で被う=納衣の下で拱手している姿(高さのある大きなお椀を伏せたような線刻模様」)という珍しい様式・形式をした石仏のことです。
全国にあまり例がない、種類の判明していない石仏
この特徴ある石仏について、なぜ私が「福重の線刻石仏 最大の謎」みたいに申し上げているかですが、大別して項目だけを先に挙げると下記の3点と思います。
(1)全国にあまり例がない石仏ではないか?
(2)この種類は何なのか?
(3)なぜ福重に集中しているのか?
上記の項目に沿って、これから補足説明をしていきたいと考えています。
1)全国にあまり例がない石仏ではないか?
全国の仏像、神像、神仏習合像の中には手印を隠した様式は、けっこうあるようです。しかし、その多くが福重の石仏と違って、「高さのあるお椀を伏せたような格好」ではなく、そこの模様全体が平べったくなっています。そのような具体的資料として、今まで福重にいらっしゃった郷土史愛好家の皆様からの仏像の写った写真、図漂や文章含めて私も見ました。
また、その中には「長崎県央地域、九州地方や奈良県にも、かなり似たような神像、仏像が何体かあるようだ」と仏像名や所在地なども具体的に教えて頂きました。また、私自身も仏像の本で調べたり、インターネットで全国あるいは中国、韓国、インドなどの仏像写真を丹念に探しました。それらの取り組みは現在も継続中すが、今までの経過を総合してみると確かに、国内にはその様式に近い仏像、神像は沢山あります。しかし、拱手した姿はあっても、福重の線刻石仏のような「高さのあるお椀を伏せたような格好」ではないのです。
これは、日本全国だけではなく遠くはインド、ガンダーラや中国などの石仏(一部木製の仏像含む)のホームページ写真を見ても、ほぼ全くないような状況です。まだまだ、今後も探し続けていきますが、現在(2012年2月)のところ、全国にも海外にも福重の線刻石仏と、ピッタリ一致する様式・形式はないと思われます。このようなことからも、この福重の線刻石仏は、全国にもあまり例のないような様式、形式の石仏と思われます。
(2)この種類は何なのか?
「福重の石仏 最大の謎」のテーマの一番は、この標題です。この前記(1)とも重複しますが、福重にある線刻石仏の種類が現時点では特定されていないからです。一体全体、お椀を伏せたような形で両手を納衣で被う=納衣の下で拱手している姿(高さのある大きなお椀を伏せたような線刻模様」)という珍しい様式・形式の石仏、神像、神仏習合像は、ずばり何と言うのかが、現在のところ「福重の石仏 最大の謎」となっています。
ここまで毎回書いて、さらに後の項目に先伸ばしするのは心苦しいのですが、このテーマは次に書く予定の別項「4)様々な説、(仮説)神仏習合像の可能性も?」と完全に重複します。そのため、次の項目で集中して書いていますので、ここでは整理上、箇条書き程度のみにします。、詳細記述ついては、後でご覧願います。
(3)なぜ石仏は福重に集中しているのか?
福重の線刻石仏は合計で14体(弥勒寺町13体、福重町1体)です。大村市内の線刻石仏、合計17体の内、武留路町の3体を除けば、他の全部が福重地区しかも弥勒寺町に、そのほとんどが集中しています。さらに弥勒寺町でも限られた所です。これは何を意味しているのか、この点も謎と言われてきました。
「なぜ石仏が福重に集中しているか?」を見る上で不可欠なことは、大村(より正確に言えば郡地区)へ、いつ仏教が伝播し仏教寺院が創建されたのかと言うことです。(この件は、先に掲載中の「大村への仏教伝播と紫雲山延命寺の標石など」なども、ご参照を)このようなことを総じて言えば仏教文化の伝わる大事な要素は、何があるかを見ることも大切と言えます。
 |
(古代に創建された)太郎岳大権現の礎石跡
(平らな4個。やや中央右端1個は重石用の石か?)
写真奥の方が三角点(大村湾)側
手前が遠目岳や南登山口側
|
私は、仏教文化の伝わる原動力を見る場合、その要素として経済と情報だと思っています。その経済の要は、水や穀物を中心とした食糧がベースになり、そこに国内外の情報(交通運輸、文化、宗教、技術、物など含む)を取り入れて進展してきたのではないかと思っています。その要素に大村で最も適していたのは、実は郡地区(松原・福重・竹松の3地区)だったのです。だからこそ、旧石器時代(野岳遺跡)、縄文・弥生時代(岩名遺跡、冷泉遺跡、沖田町にある黒丸遺跡)、古墳時代(黄金山古墳、野田古墳)など、たくさん出土しています。
つまり、縄文・弥生時代から長崎県下有数の穀倉地帯で人が多く住んでいて、肥前国分寺(佐賀市大和町)など創建された佐賀県とも郡地区は、「大村の古代の道と駅」などを使えば位置関係で隣になるので仏教含めて様々な情報が伝わりやすかったと言うことです。なお、この肥前国は、「大宝令の施行された702年(大宝2)前後には成立していたとみられる(長崎県史古代・中世編)」と言われています。また、天平13(741)年に国分寺と国分尼寺の国ごとに建立の詔(みことのり=天子の命令)を発し、全国各地に例えば肥前国分寺など多数が創建されました。
このような仏教の経過だけから考えても、郡地区は佐賀県の隣と言う位置関係からしても、何百年も遅れて従来説=「大村へ中世時代に仏教が伝わり、寺院もこの時期に初めて創建された」みたいには思えないのです。このことは、さらに平安時代末期製作の福重にある経筒、単体仏などをご覧頂くと一層分かりやすいので、先の項目「従来説(大村への仏教伝播、古い寺院と石仏建立は中世時代説)は間違い」も参照願います。また、大村郷村記によれば、奈良時代初期に建立された太郎岳大権現の礎石跡(右上側写真参照)も郡岳(826m)頂上に現在も残っていますので、登山の機会にご参照願います。
物事の進展は、なんでも基本やベースが大切と言われています。仏教の伝播や寺院の創建も同じことが言えるでしょう。今回のテーマである福重の線刻石仏についても、先に述べた経済、情報を始め交通便利な位置関係などから郡地区の福重は、最初から石仏が沢山建立される要素があったと見る方が、むしろ自然だったと思えます。
地名からも考えて
ここで、直接関係あるかないか不明ながら、地名について書きます。なぜ、地名を取り上げるかと言いますと、私は以前「福重郷土史講座」で講師の方から「地名が定着する(根付く)には400年、500年ではダメで、それ以上かかる」と聞きました。また、その地名には、その地域に元々あった由緒(歴史事項)も含めて独特の例えば風土・風習・名物・物語・宗教などに起因して付いた名称も、けっこうあるそうです。
 |
石仏の多い弥勒寺町周辺(中央部から右側方向)
(後方右側の山は郡岳)
|
そのようなことから、私は、福重の石仏が集中している弥勒寺町、福重町の旧・字(あざ)で仏教と関係ありそうな地名に関心を持ってもいました。ここで、その地名と、その名前の付いた要因と思えることを、私の推測も含めて、ご参考までに下記に書いておきます。何か今回の地名紹介だけで「”謎の石仏”を解き明かす」と言うものでは決してありませんが、これらの地名からも興味引かれるものがあります。(下記<>内は、国語辞典の大辞泉より)
・上八龍、下八龍=八大龍王と関係あるのではないか。注:この二つの地名には上八龍の線刻石仏と下八龍の線刻石仏がある所である。<八大龍王=法華経賛嘆(さんだん)の法会に列した8体の護法の竜王。難陀(なんだ)・跋難陀(ばつなんだ)・沙伽羅(しゃがら)・和修吉(わしゅきつ)・徳叉迦(とくしゃか)・阿那婆達多(あなばだった)・摩那斯(まなし)・優鉢羅(うはつら)の八竜王。雨をつかさどるという。>
・釈迦峰=現在行方不明の「お釈迦様の足形石(仏足石)」が、この地名の石走川沿いにあった。この地名近くに上八龍の線刻石仏がある。<仏足石=ぶっそくせき、釈迦の足の裏の形を表面に刻んだ石。インドの初期仏教では仏がそこにいることを示すしるしとして用いたが、のち礼拝の対象とされ、千輻輪(せんぷくりん)などの図が刻まれる。日本では奈良の薬師寺にあるものが最古で、天平勝宝5年(753)の銘がある。>
・赤坊園=坊は、寺院の本坊、脇坊などを指して言う。注:この地名の所には、石堂屋敷の線刻石仏B、石堂屋敷の線刻石仏D、石堂屋敷の線刻石仏Gなど合計9体の線刻石仏が集中している。
・強力=大村郷村記によれば奈良時代の和銅年間に開山されたと言う太郎岳大権現(郡岳826mの旧称)へ登山する僧侶や修験者をサポートする人たちが住んでいたとも思われる所か。(この強力の地名だけが福重町、上記の他の地名は全て弥勒寺町である)
以上、全国どこの地名にも大なり小なりの異説もあるので、全て上記の由来通りとは断定できませんが、それにしても他にないような仏教に関連した地名とも思えます。特に、弥勒寺町で線刻石仏のある所は、石仏の集中度合いが高いだけでなく、仏教に関連している地名も集中していると言えます。
(補足) 山岳密教と修験道について
大村郷村記によれば郡岳(こおりだけ、826m)の旧称である太郎岳に太郎岳大権現が奈良時代の初期に開山されていたので、福重町(旧・矢上郷)の石走付近には、その一の鳥居もあったとの伝承もあります。(注:念のため、この太郎岳大権現の「奈良時代開山説」が間違いで仮に「平安時代のか言開山説」となったしても今回の福重の石仏シリーズには時代的な大きな影響はなく、どちらの時代でも考え方は同じと言えます。なお、ご参考までに、この太郎岳大権現は、大村郷村記によれば文明年間(中世時代)に多良岳に移転しています)
福重町の隣でもある弥勒寺町含めて福重地区には太郎岳(郡岳)への修験道が何本かありました。特に、弥勒寺町の石走川沿いを通る修験道の2本は、その中心だったと思われます。同時にその山岳密教・山岳宗教と関連して仏教が栄え、その一つの表れとして修験道近くの山麓で線刻石仏があったとの仮説は、ある種納得性も出てきます。(この修験道の件は、『大村の古代の道、福重の修験道』ページも、ご参照願います)
4)様々な説、(仮説)神仏習合像の可能性も?
福重の石仏を直接見学された方は、私が同行あるいは案内役をした分を含めれば既に百名を越えています。また、その中の数十名には、仏像・郷土史関係の先生や郷土史愛好家もいらっしゃいました。その後、電話や電子メールなどでも意見や感想が私の方へ寄せられました。そのような方々から、福重の線刻石仏について、神像、神仏習合像、仏像など、実に様々な説をお聞きしました。その内容のいくつかは、既に先の項目に書いています。
福重の線刻石仏について寄せられた意見の集約
先の項目内容と重複しますが、私が覚えている範囲内で改めて皆様方の意見や感想を再度書こうと思っています。なお、意見の中には調査段階中ばかりですから、結論を持って述べられたものではないのですが、今回あえて便宜上、<神像系>、<神仏習合像系>、<仏像系>に分けて皆様から寄せられた意見を下記に集約してみました。当然のことながら、どの意見も重なり合っていることは、あらかじめご了承願います。
<神像系の意見>
・「拱手している姿は神像の特徴であると思う」
・「両手を納衣で隠しているところがポイントだ。拱手しているので神像ではないか?」
・「蓮華座も光背もないので、これは仏像ではない。神像かもしれない」
<神仏習合像系の意見>
・「蓮華座がないので従来の仏像ではないのではないか?」
・「仏像には大抵ある光背がない」
・「こんなに沢山あるのに蓮華座が一体もない石仏は、見たことがない」
・「あなた方は石仏(仏像)と呼んでいるが、仏像と言うより神像あるいは神仏習合像ではないか?」
<仏像系の意見>
・「こんなにたくさん、石仏(線刻石仏)があるとは知らなかった」
・「色々と細部は違うところもあるが、全体の形自体は、どこでも見るような如来系の石仏ではないだろうか?」
・「これは本地仏を表示するための仏形(けぶつ、用語解説参照)に似たような、同じような仏像があった」
・「この形は修業中の僧侶を表しているのではないか?」
・「神像ならば、こんな狭い地域に沢山ある訳がない。仏様なら一か所に沢山ある所も今まで見てきたが・・」
などの意見や感想でした。このような意見は、2012年2月現在の集約です。そのため、今後も続くと思いますので新たな意見や主張などがあれば、このページに追加掲載も検討していきます。
あと、意見だけでなく、ある熱心な方は、わざわざA3サイズ位の写真数枚を持参されて「福重の線刻石仏は、この写真の仏像、神像に似ている。参考にならないか」などと具体的に教えて下さった例もありました。しかし、今までどなたも確信持って断定的に(正確に)、「この福重の線刻石仏は・・・・と言う種類の仏像、あるいは神像だ」みたいなことは聞きませんでした。
ですから、上記の「」内の各意見も、いずれも断定的な書き方は出来ないと思い、お聞きした通りのまとめ方をしています。つまり、福重の線刻石仏については、今なお誰も結論が出ていない、明確に分かっていない「謎の石仏」と言うことです。
・仏像、神像、神仏習合像の補足
色々と多く述べた後になって、改めて仏像、神像、神仏習合像の姿や形の違いを言うのは可笑しいのかもしれませんが、5年以上も前のことを書きます。当初、私は仏像、神像の明確な違いが分かりにくい時期もあり、全体の形自体に、びっくりするほどの違いはないとも思っていました。たとえが適切でないかもしれませんが、同じ車であっても乗用車とトラック車の違いが分かるほど、直ぐには分からなかったと言うことです。
また、一般に「仏像には蓮華座や光背があるはずだ、神像や神仏習合像には、それが付いていない」みたいに言われる方もいます。しかし、その説明も成り立つ場合もありますが、実は私が色々な写真を見たところ、神像にも蓮華座や光背の付いている形もありました。逆に、仏像と分かっていても蓮華座や光背がないのもありました。
なぜ、こうなっているかと言いますと、(本来は大事なことなので詳細に書かないといけない事項ですが、今回簡単に表現をしますと)日本古来の神様には元々崇拝する像はなくて、中国などから伝来した仏教との関係から仏像の形を真似して神像、神仏習合像が出来たとも言われています。
もちろん、その中には女神・男神の違い、座像・立像あるいは木像・石像の作りの差などはありますが、体にまとっている衣も両方とも当時の衣類ですから全体に似ていると思われます。さらに仏像、神像を同じ製作者が作ったとすれば、それも形は似てくるのではないでしょうか。
あと、像を見る場合、全体の形とか身にまとっている衣類と言うのは、部分を見るより、私は印象に残る意味では大きいような気もしています。ここで、現実にはあり得ない奇想天外な発想ですが、もしも、仏像が最初に作られた当時が近代と同じような服装類だったとしたら、「男の仏像・神像なら背広とネクタイ姿」、「女の仏像・神像なら着物か洋服姿」みたいな像もできたかもしれないです。
つまり、仏像・神像の身にまとうものは、その当時の衣類などが基本形となり、部分的には日本独自の様式も加わり変化しながらも継続されてきたから現在見るような姿・形なのではないでしょうか。ですから強引な見方になりますが、部分は違っていても仏像も神像も神仏習合像も、全体的には大きな違いに見えないのかもしれません。
このようなことを書けば「いや、それは違う。仏像の種別は直ぐ分かる」と言われる方もいらっしゃるでしょう。ならば、「なぜ、謎とも呼んでいる福重の線刻石仏の種別が、専門家をもってしても直ぐに分からないのか」との反論もあろうかと推測します。ここから、仏像、神像、神仏習合像のほんの一例をご紹介します。ただし、下記の種別は私が便宜上分けただけで、専門的に種類別に表示されている訳ではありません。下記<>内の文字をクリックして、ご覧頂けないでしょうか。
・仏像の代表例=(奈良市観光協会ホームページの)<東大寺大仏、毘盧遮那仏>
・神像の代表例=(薬師寺ホームページの)<三神像(国宝、平安時代)>、(文部科学省ホームページの)<(国宝)木造熊野速玉大神坐像 (もくぞうくまのはやたまおおかみざぞう) ・木造夫須美大神坐像 (もくぞうふすもおおかみざぞう) ・木造家津御子大神坐像 (もくぞうけつみこおおかみざぞう) 注:ページ中段に写真あり>
・神仏習合像の代表例=(福井の文化財ホームページの)<十一面女神坐像>(上野注:この像は十一面観音ですから頭部に、その特徴が表れています。しかし、仮に頭部が極普通の仏像としたら、拱手している姿などは福重の線刻石仏にも似たところがあります)
上記のリンク先から見る写真や説明文章を読むと、仏像、神像、神仏習合像の違いも理解できるかもしれません。ただし、説明文章なしの写真だけ何十枚かバラバラに机の上に置いてあって、そこから「正確に3種類別の箱に分けて入れなさい」と指示が出されたとしたら、はたして全部を正解できるでしょうか。特に、神像、神仏習合像の違いは、なかなか容易には分かりにくいと思われます。
なぜ、このようなことを書いているかと言いますと、福重の線刻石仏は、姿・形だけで判断したら間違った評価をしてしまうのではないかと言うことです。目に直ぐに見えるものだけなく、福重の歴史、宗教、地域の事柄全般なども含めて、石仏を見ていく必要性があるのでないかと改めて思っています。
神仏習合についての大村の特徴
まず、神仏習合(神仏混淆)について、国語辞典の大辞泉に次の<>内のことが書いてあります。<日本固有の神の信仰と外来の仏教信仰とを融合・調和するために唱えられた教説。奈良時代、神社に付属して神宮寺が建てられ、平安時代以降、本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)やその逆の反本地垂迹説などが起こり、明治政府の神仏分離政策まで人々の間に広く浸透した。神仏混淆 >
神仏習合の歴史について様々な説もありますが、上記辞典内容も参考に考えれば仏教が(538年)中国などから伝来し、その後から明治維新頃(1868年)まで約1300年間くらい続きました。一旦は明治政府の神仏分離令などで廃仏毀釈(はいぶつきしゃく、用語解説参照)まで起こりましたが、後年に復活した状況もあります。大村市内での具体例が分かりやすいと思いますので、いくつか下記事項を挙げます。(念のために下記内容の一部は全国にもあるものです)
 |
石堂屋敷の単体仏(弥勒寺町)
(経筒を埋めた経塚の上にあったと言われている)
|
 |
(古代に創建された)太郎岳大権現の礎石跡
(平らな4個。やや中央右端1個は重石用の石か?)
写真奥の方が三角点(大村湾)側
手前が遠目岳や南登山口側
|
(イ)大村郷村記によれば太郎岳大権現(奈良時代初期、和銅年間=708〜715年に開山、戦国時代の文明年間=1469〜1487年に多良岳に遷座して、後世、多良大権現や金泉寺と呼ばれている)が、大村で最も古い神仏集合の寺院と思われる。(太郎岳大権現の詳細は、ここから参照)
(ロ)大村市内に沢山ある「・・・権現様」と呼ばれている神社は、ほぼ全て神仏習合である。今では大きな社(やしろ)や境内を有し、一般には「・・・神社」と呼ばれているが、明治維新前まで神仏習合の形だった所も、江戸時代編纂の(大村)郷村記に見られる。
(ハ)古くからある民家や農業地域などの各家に多くある台所・火の神様である荒神様(こうじんさま)は、国語辞典の大辞泉によれば<「三宝荒神(さんぽうこうじん)」の略。 民間で、かまどの神。また、防火・農業の神>と書いてある。さらに三宝荒神の意味は、<仏・法・僧の三宝を守護するという神> と解説してある。つまり、仏教を守る神様でもある。なお、ご参考までに全国的にも有名な清荒神(兵庫県宝塚市にある)は、真言三宝宗・清荒神・清澄寺にあり、仏教寺院である。
(二)(上記に関連して)大村市寿古町には竈権現(かまどごんげん)があるが、この建物や鳥居跡などは一見して神社系と思われるが、毎年の例祭は福重町にある(仏教寺院の)妙宣寺に来てもらって執り行われている。このことは、(大村郷村記によれば)江戸時代から継承されている。
(ホ)大村市内に古くからある民家(仏教の檀家)の例として、お葬式があった場合、当日に神主さんに来て頂いてお祓いをしている。(他県出身者などから来られた会葬者の中には、これらについて不思議な顔をされる場合もある)
以上、大村市内には、まだまだ、神仏習合(神仏混淆)の事柄例などが多く残っていと思われます。もしも、大村郷村記通り、太郎岳大権現の開山年が正しければ、この神仏習合の歴史は約1300年続いていることになります。明治政府の神仏分離令などで一旦は途絶えたかにみえた信仰ですが、民衆の心は長年続けてきたことでもあり、簡単には全部絶えなかったと言うことでしょう。また、大村だけではなく、日本全国も同様かもしれません。
なお、このようなことは大昔から「八百万(やおよろず)の神様・仏様」という言葉もある通り、天変地異の多い国土ですから自然を敬い・畏れ、極普通に多くの信仰をしてきた日本人の民族性もあるのではないでしょうか。また、現在では一神教しかない国や地域では、日本古来の歴史や風習は、あまりないようにも思えます。(蛇足ながらイタリア・ローマにはパンテオン(八百万の神)がキリスト教が広まる前頃までは信仰されていたと言う。詳細は「驚異のローマ建築、「八百万の神様 パンテオン」ページ参照)
このように長い歴史が続く大村の(正確に言えば、その中でも郡地区の)土地柄ですから、(この事柄は)「仏教だ」、「神道だ」、「神仏習合だ」と言う明確な区分けは大昔から存在しなかったと思われます。そして、私達が石仏と呼んでいる福重の線刻石仏も、その様な状況の中で建立されたとも思えます。
--------(下記原稿、準備中。しばらくお待ち下さい)------
様々な説から神仏習合像の可能性もあるのではないか
(原稿準備中)
まとめ
(原稿準備中)
|